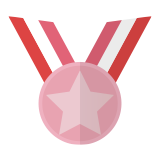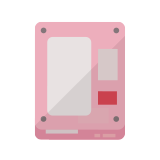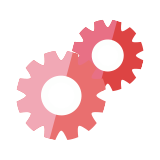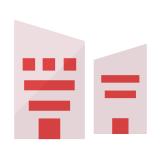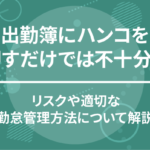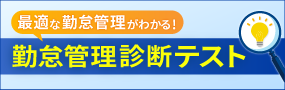柔軟な働き方が魅力のフレックスタイム制!そのデメリットとは?
勤怠管理システム
働き方改革
ナレッジ

ワーク・ライフ・バランスを高め、柔軟な働き方が可能となるフレックスタイム制。従業員にとっては、プライベートの充実や、ストレスを軽減できるところが魅力です。
また、企業にとっても無駄な残業時間の軽減、優秀な人材の確保・定着がしやすいというメリットがあります。このように、フレックスタイム制は従業員側にも企業側にも恩恵がある勤務スタイルです。それでは逆に、どのようなデメリットがあるのでしょう?
今回は、フレックスタイム制のデメリットについてご紹介します。フレックスタイム制導入の際の参考になさってください。
目次
フレックスタイム制のデメリット
フレックスタイム制のデメリットについて見ていきましょう。
従業員の自己管理能力に委ねられる
従業員自身が出勤時間や退勤時間をフレキシブルに決めることができるフレックスタイム制。自由に働くことができる分、総労働時間の確保等を考慮しながら計画的に勤務する必要があります。そのため、自己管理能力の低い従業員の場合、ルーズな状態を助長してしまい、フレックスタイム制がマイナスの方向に働いてしまう場合もあります。
従業員間のコミュニケーション不足
従業員の出勤時間・退勤時間がそれぞれ異なるため、従業員同士が顔を合わせる機会が減りやすく、コミュニケーション不足に陥る可能性があります。従業員間でのコミュニケーションを図れる社内ツールなどを活用し、コミュニケーション不足を解消することができる取り組みをすることが必要です。
電話対応や急な会議に対応できない
フレックスタイム制では、時間帯によっては社内に従業員が不在となる場合があります。それにより、取引先や顧客からの問い合わせ等の電話に対応できないという不都合が生じることもあります。また、急な会議を行いたい場合などにも、従業員の対応が難しい場合があります。
光熱費がかさむ
従業員の出勤時間・退勤時間にバラつきがあるため、従業員が会社に滞在する時間は長くなります。そのため、空調や照明の使用頻度が増え、経費がかさんでしまう場合もあります。
フレックスタイム制の概要
そもそもフレックスタイム制とはどのような勤務形態なのでしょうか?
フレックスタイムは、1987年の労働基準法改正により、1988年の4月から導入が開始された制度です。清算期間・総労働時間を決め、出勤時間や退勤時間の決定は労働者に委ねられます。「9:00~17:00」のような画一的な働き方ではなく、ライフスタイルに合わせた勤務が可能です。
例えば「子どもの保育園の送迎時間に合わせたい」、「通勤ラッシュ時間を避けて出社したい」など、従業員の希望に合わせた働き方をすることができます。
フレックスタイム制には、時間の選択によって労働することができるフレキシブルタイム、必ず労働しなければいけないコアタイムが設定されています。すべてをフレキシブルタイムにすることも可能ですが、フレキシブルタイム・コアタイムの両方を組み合わせて取り入れているケースが多いようです。
フレックスタイム制の導入がおすすめな職種

フレックスタイム制の導入が向いている職業にはどのようなものがあるのでしょう。例えば、研究・開発者、編集者、デザイナー、エンジニア、クリエイターなど、技術的な業務、個人での業務が主となっている職種は、フレックスタイム制に向いている職種といえます。
逆に法人営業のように、他の企業との取引が多い職種にはフレックスタイム制の導入は適していないといえそうです。法的にはフレックスタイム制の導入可能な職種に対する制限はなく、幅広い企業・職種で取り入れられています。
フレックスタイム制度の導入方法
では、フレックスタイム制を導入するためにはどのように行えばいいのでしょうか?フレックスタイム制を導入する際は、2つの条件を満たす必要があります。
労使協定を締結する
フレックスタイム制の基本的な部分を労使協定で定めることが必要です。具体的には次のような項目があります。
- 対象労働者の範囲
- 清算期間の長さ(1ヵ月以内)
- 清算期間の起算日
- 清算期間での総労働時間
- 1日の標準労働時間
- コアタイム・フレキシブルタイム
企業はこれらの内容を、労働組合、または労働者の過半数の代表者と締結します。
就業規則への規定
フレックスタイム制を導入する場合、就業規則に「始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねる」との明記が必要です。始業時間・就業時間についても、記載が必須です。
また、フレックスタイム制導入の際は、導入の意義を明確にしておくことも大切です。
フレックスタイム制の労働時間・時間外労働時間の管理方法
フレックスタイム制では、日々の労働時間が変動するので、週ごとや月ごとに労働時間を設定します。週ごと・月ごとに労働時間を設定する期間のことを清算期間といいます。
この清算期間内における総労働時間が、通常の会社における定時のような基準時間になります。総労働時間は企業が設定することができますが、それには上限があります。フレックスタイム制の企業の場合、週40時間あるいは月に何時間以内という総労働時間を定めなくてはいけません。
例えば、月の日数が28日の場合は160時間、31日の場合は177.1時間という時間になります。計算式は、「清算期間における総労働時間≦(清算期間の暦日数)÷7日×40日」となります。
この総労働時間を超えると、残業とみなされますのでフレックスタイム制でも残業代を支払わなくてはいけません。逆に総労働時間に満たなかった場合は、給与をカットしたり、労働時間を翌月に繰り越したりして対応します。
フレックスタイム制の導入意義を明確に
柔軟なフレックスタイム制は、従業員にとっても企業にとってもメリットのある制度です。しかし、従業員の意識次第でフレックスタイム制がマイナスに作用してしまう場合もあります。メリット・デメリット、またフレックスタイム制が適した職種・企業であるかも考慮して制度の導入を検討しましょう。また、社内の意識を統一させるためにもフレックスタイム制の導入意義をはっきりとさせておくことも重要です。