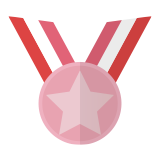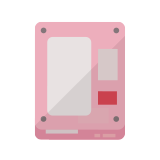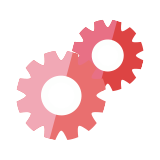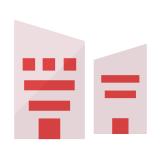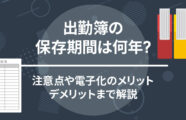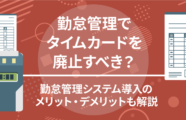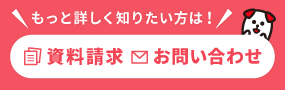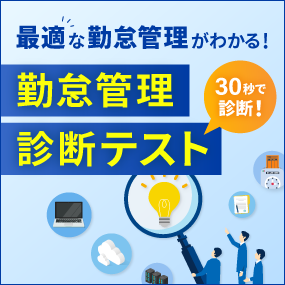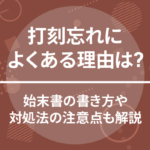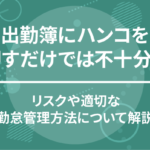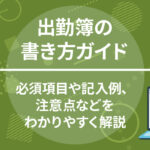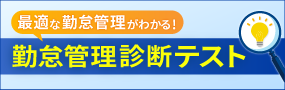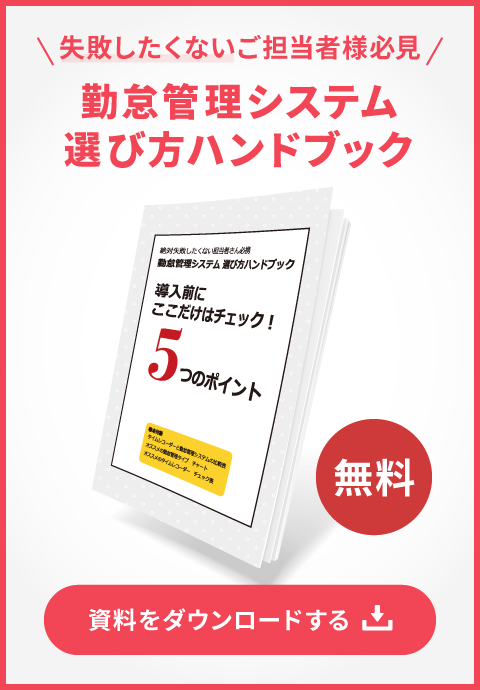勤怠管理システムの自作は可能?作り方やポイント、注意点などを解説
勤怠管理システム
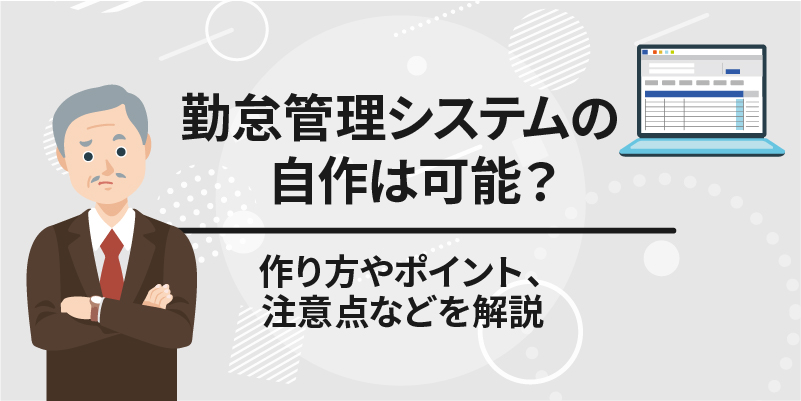
公開日:2025年7月4日
こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。
勤怠管理システムを導入すると、業務効率や正確性の向上などのメリットを期待できます。勤怠管理システムは既製品を利用するケースが大半ですが、システムを自作したいと考える企業も少なくありません。
本記事では、勤怠管理システムを自作する手段やポイント、具体的な手順や注意点などを解説します。
目次
勤怠管理システムを自作することは可能?
結論からいうと、勤怠管理システムは自作が可能です。企業が勤怠管理システムを導入する際は、ベンダーが提供するサービスを利用する場合が一般的です。しかし、「なるべくコストをかけたくない」「従業員数が少ないのでシステムを導入するほどではない」「独自の就業ルールに合わせたい」などの理由から、勤怠管理システムを自作する企業もあります。
勤怠管理システムを自作するメリット
自作の勤怠管理システムには、ベンダー提供のサービスと比べて以下のようなメリットがあります。
自社の課題やルールに合わせて設計できる
自作の勤怠管理システムは、柔軟性の高さが魅力です。それぞれの課題やルールに合わせた設計が可能なため、自社にとって使いやすいシステムを導入できます。
フレックスタイム制や変形労働時間制などの複数の勤務形態を採用している場合や、部署ごとにルールが異なる場合にも、フレキシブルな対応が可能です。
コスト削減につながる
ベンダーが提供するサービスを利用するためには、月額利用料などのランニングコストが必要です。また、自社の勤務ルールに合わせたカスタマイズを行う場合は、追加料金がかかる可能性があります。その点、自社でシステムを開発すれば、開発や運用・保守にかかる外注費を削減できます。
勤怠管理システムを自作する手段
勤怠管理システムを自作する方法は、「ExcelやGoogleスプレッドシート」と「システム開発」の2パターンに分けられます。
Excelやスプレッドシート
ExcelやGoogleスプレッドシート(以下、スプレッドシート)での勤怠管理といえば、出退勤時間を記録するだけのシンプルなものを思い浮かべる人も多いでしょう。しかし、関数やマクロを活用すれば、労働時間の集計や休暇の申請処理などの自動化も可能です。
また、元々Excelやスプレッドシートを使用している職場であれば導入コストもかからず、操作方法のレクチャーの手間も軽減されます。
システム開発
より高度で自由度の高い勤怠管理システムを作成したい場合は、システムの自社開発がおすすめです。多様な打刻方法に対応したり、複雑な業務フローに対応させたりと、自社のニーズに合うシステムを自由に設計できます。
システム開発には「Java」や「Python」などのプログラミングスキルが必要ですが、最近はソースコードを記述せずにシステム開発ができるツールも登場しており、従来よりもハードルは低下しています。
勤怠管理システムの代表的な機能
ここからは、システム開発をしたい人に向けてお話します。勤怠管理システムに搭載したい基本機能について、「従業員向けの機能」と「担当者向けの機能」をそれぞれ紹介します。
従業員向けの機能
従業員向けの代表的な機能は、「打刻機能」「ワークフロー機能」「アラート機能」の3つです。
| 打刻機能 | 従業員が出退勤時刻や休憩の開始・終了を記録する。休憩時間の記録に関しては、勤務時間に応じて自動で算出できるようにする場合もある。 |
|---|---|
| ワークフロー機能 | 従業員が有給休暇や残業などを申請し、承認を受けるための機能。有給休暇の残日数の管理にも対応させる場合が多い。 |
| アラート機能 | 残業時間を超過しそうな従業員に対して、アラートを表示させる。 |
担当者向けの機能
担当者向けの代表的な機能は、「勤怠データの集計機能」「シフト管理機能」「ほかのシステムとの連携機能」の3つです。
| 勤怠データの集計機能 | 従業員の労働時間や勤務日数、残業などの勤怠データを集計する。そのほか、深夜労働や休日出勤、有給休暇の取得情報なども管理する。 |
|---|---|
| シフト管理機能 | 従業員の勤務スケジュールを管理する。打刻機能や集計機能との連携により、統合的な勤怠管理が可能となる。 |
| ほかのシステムとの連携機能 | そのほかのシステムとのAPI連携やデータベース連携、ファイルのインポートやエクスポートなど。 |
勤怠管理システムを自作する基本手順
ここからは、システム開発によって勤怠管理システムを自作する場合の、おおまかな手順を紹介します。
1.データベースを設計する
まずは、従業員氏名や従業員番号、出退勤時刻など、勤怠管理システムで管理する項目を検討し、データベースを設計しましょう。Excelやスプレッドシートを活用する場合も、管理する項目をシートやファイルにまとめておきます。
2.システム構造について検討する
次に、実装する機能や、機能同士の連携について検討しましょう。システム構造を検討する際は、自社の勤務体系を整理することが大切です。従業員の勤務形態を把握し、全てのケースに対応できるように考慮します。
3.他のシステムとの連携について検討する
勤怠管理システムを給与計算システムや人事管理システムなどと連携させると、業務効率をさらに高められます。どのシステムと連携させるか、どのように連携させるかといったポイントを検討しましょう。
4.自社に合わせた打刻方法を選択する
タイムレコーダーやICカード、生体認証など、勤怠管理システムの打刻方法はさまざまです。勤務形態や在宅勤務の有無などを踏まえ、自社に合わせた打刻方法を選択しましょう。その際、不正打刻の防止対策についても検討することが大切です。
5.システムを設計・開発する
ここまでの検討内容を踏まえて、自社に合わせて勤怠管理システムを設計します。このとき、法改正に迅速に対応できるような設計にすることが大切です。
なお、システム設計図は必ず作成しておきましょう。システム設計図を作成したら、そのとおりに開発を進めていきます。システム設計図があると、前任者が退職した場合も、運用・保守を継続しやすくなります。
勤怠管理システムの自作を成功させるポイント
勤怠管理システムの自作を成功させるためには、次のポイントを押さえることが大切です。
導入目的を明確化する
「勤怠管理業務を効率化したい」「さまざまな働き方に対応したい」など、勤怠管理システムの導入目的を明確にしましょう。導入する目的が明確になれば、自社が必要とする機能の洗い出しができます。
自社の勤務形態やルールを整理する
自社の勤務形態や勤怠ルールを整理することも重要です。フレックスタイム制やシフト勤務、夜勤などの従業員の働き方と、それぞれの勤怠管理や給与計算のルールを確認しましょう。
勤怠管理システムの導入は、新しい働き方を始めるよい機会にもなります。これから導入予定の勤務形態がある場合は、その働き方にも対応したシステムを設計しましょう。
補助金を活用する
システム開発にかかるコストを低減したい場合は、補助金の活用もおすすめです。具体的には、以下のような補助金を申請できる可能性があります。
- IT導入補助金
- ものづくり補助金
- 事業再構築補助金
- 小規模事業者持続化補助金
また、上記のような国の制度のほかに、各自治体の補助金制度を利用できる場合もあります。
自作の勤怠管理システムを運用する際の注意点
自作の勤怠管理システムの運用において、注意したい4つのポイントをまとめました。
法改正への対応が必要
労働者の労働時間や休日などについては、労働基準法により厳格なルールが定められています。しかし、労働関連法は頻繁に改正され、その都度、改正された内容を勤怠管理システムに反映しなければなりません。
ベンダーサービスを利用する場合は自動的にアップデートされますが、自作のシステムを利用する場合は迅速かつ適切な対応が必要です。
Excel管理は不正やヒューマンエラーが起こりやすい
Excelやスプレッドシートによる勤怠管理システムでは、従業員の自己申告に基づき出退勤時刻を入力するため、不正申告を完全に防ぐことは困難です。また、数字の打ち間違いといったヒューマンエラーも起こりやすく、勤怠データの正確性が低下する恐れがあります。
メンテナンスが属人化しやすい
多くの企業では、システム開発に必要な知識やスキルを持つ人材は、一部の従業員のみです。システムのトラブルやメンテナンス時にも、対応できる従業員が限られるため、業務の属人化を招きやすい傾向があります。
システムに関わる業務が属人化してしまうと、担当者の不在時や退職時にシステム運用が滞りかねません。
コストが増大する可能性もある
システムの開発や保守・運用は、膨大なコストを必要とします。多くの担当者は開発業務にほとんどのリソースを割かれ、通常業務に手が回らなくなってしまうでしょう。その結果、全体の業務効率が低下する恐れがあります。
ベンダーの利用料や依頼料が発生しないことで短期的なコストは抑えられますが、長期的にみるとコストが増大してしまう場合もあります。/p>
勤怠管理システムを導入するならクラウドサービスがおすすめ
勤怠管理システムを自作すると、かえってコストが高くなる可能性がある上に、担当者にも負担がかかってしまいます。自社リソースでの対応が難しい場合は、ベンダーサービスの利用も検討しましょう。
導入にかかるコストや負担を軽減したいなら、クラウド型の勤怠管理システムがおすすめです。初期費用無料で利用できるサービスもあり、導入のハードルが低いです。普段の運用管理や法改正への対応もベンダーに一任できるので、担当者への負担が少なく済みます。インターネット環境さえあればいつでも、どこでも利用できる点もメリットです。
まとめ
勤怠管理システムは、Excelやスプレッドシート、システム開発などにより自作が可能です。自作の勤怠管理システムは柔軟性の高さやコストの低さが魅力ですが、専門的な知識やスキルが必要なので、かえってコストが上がってしまう場合もあります。
勤怠管理システムを導入するなら、タッチオンタイムをぜひご検討ください。「タッチオンタイム(Touch On Time)」は、株式会社デジジャパンが提供する、市場シェアNo.1※の勤怠管理システムです。専属のサポート担当がついており、追加費用なしで電話サポートが利用できます。あらゆる職場にフィットする独自のタイムレコーダー(TOTレコーダー、Facee)で、労働条件に影響されることなく打刻が可能です。
※2023年 富士キメラ総研調べ 勤怠管理SaaS市場 利用ID数
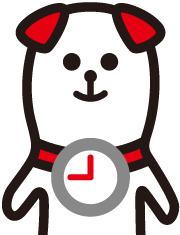
- この記事の執筆者
- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
- 受賞歴:「BOXIL SaaS AWARD Spring 2025」勤怠管理システム部門
ITトレンド Good Productバッジ 2022